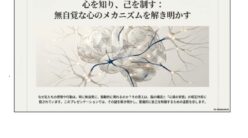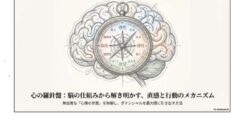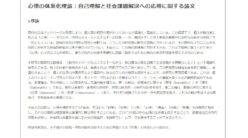この体系化は、「心得(意識、思考、環境、体調)」の「手法(スキル)」の定義です
1)「心得」の手法
ここでは、「印象、相関、心情」の体系化より導いた「心得」の手法を提案する
<提案内容>
・心情の育成方針(成長過程、成長タイプ)
・心情の意識改善(印象確認、目標設定)
・心情の思考改善(思考維持、思考回避)
・心情の環境改善(環境対策、体調管理)
<心情の育成方針(成長過程、成長タイプ)>
図2.イメージ状態とエネルギー状態(幼少期)
プラス プラス
| ++++ | ++++
| ++++ | ++++
| ++++ | ++++
社会ーーーーーーー+ーーーーーーー個人 社会ーーーーーーー+ーーーーーーー個人
| ---- | ----
| ---- | ----
| ---- | ----
マイナス マイナス
「イメージ状態」 「エネルギー状態」
[+:欲求、-:抑圧、*:活力、0:制約] [+:欲、-:疑、*:愛、0:無]
図3.イメージ状態とエネルギー状態(成長・成年期)
プラス プラス
**** | ++++ **** | ++++
**** | ++++ **** | ++++
**** | ++++ **** | ++++
社会ーーーーーーー+ーーーーーーー個人 社会ーーーーーーー+ーーーーーーー個人
0000 | ---- 0000 | ----
0000 | ---- 0000 | ----
0000 | ---- 0000 | ----
マイナス マイナス
「イメージ状態」 「エネルギー状態」
[+:欲求、-:抑圧、*:活力、0:制約] [+:欲、-:疑、*:愛、0:無]
「成長過程」は、以下の通りになる
「幼稚園の入園前(幼少期:0歳~3歳)」 ※図2.イメージ状態とエネルギー状態(幼少期)※
「イメージ状態」
・この時期は「脳内が最初の学習を始めた段階で周囲を気にしない状態」のため、「感性x自律」の解
釈による学習(記憶)が多く、心情の「イメージ状態:欲求のイメージ」が強い
※環境や体調に問題がある場合※
「環境や体調が気になる状態」のため、「感性x他律」の解釈による学習が増え、心情の「イメー
ジ状態:抑圧のイメージ」を強くする可能性がある
・「欲求のイメージ」が強いと、「好奇心、ワクワク」の直感が増える
・「抑圧のイメージ」が強いと、「猜疑心、ザワザワ」の直感が増える
「エネルギー状態」
・この時期は「脳内が最初の学習を始めた段階で周囲を気にしない状態」のため、「感性x自律」の解
釈による影響(是認)が多く、心情の「エネルギー状態:欲のエネルギー」が強い
※環境や体調に問題がある場合※
「環境や体調が気になる状態」のため、「感性x他律」の解釈による是認が増え、心情は「エネルギ
ー状態:疑のエネルギー」を強くする可能性がある
・「欲のエネルギー」が強いと、「喜び、笑い、愛好」の感情が増える
・「疑のエネルギー」が強いと、「苦しみ、叫び、嫌悪」の感情が増える
「心情の状態」
「欲求のイメージⅹ欲のエネルギー」の場合
・「欲求のイメージ」の行動トリガーは、「やりたい」の欲求から「好奇心」の直感が生まれ、「欲のエネ
ルギー」の行動ジャッジは、「自分が熱中する」状態で自分の直感を「許可する(諦めない)」判断にな
るため、「好奇心」を肯定した自律的な「行動」と「感情(喜び、笑い、愛好)」が現れやすくなる
「抑圧のイメージⅹ疑のエネルギー」の場合
・「抑圧のイメージ」の行動トリガーは、「やりたくない」の抑圧から「猜疑心」の直感が生まれ、「疑の
エネルギー」の行動ジャッジは、「周囲に過敏になる」状態で自分の直感を「許可しない(諦める)」の
判断になるため、「猜疑心」を正当化した他律的な「行動」と「感情(苦しみ、叫び、嫌悪)」が現れや
すくなる
「欲求のイメージⅹ疑のエネルギー」の場合
・「欲求のイメージ」の行動トリガーは、「やりたい」の欲求から「好奇心」の直感が生まれ、「疑のエネ
ルギー」の行動ジャッジは、「周囲に過敏になる」状態で自分の直感を「許可しない(諦める)」判断に
なるため、「好奇心」を正当化した他律的な「行動」と「感情(苦しみ、叫び、嫌悪)」が現れやすくなる
「抑圧のイメージⅹ欲のエネルギー」の場合
・「抑圧のイメージ」の行動トリガーは、「やりたくない」の抑圧から「猜疑心」の直感が生まれ、「欲の
エネルギー」の行動ジャッジは、「自分が熱中する」状態で自分の直感を「許可する(諦めない)」判断
になるため、「猜疑心」を肯定した自律的な「行動」と「感情(喜び、笑い、愛好)」が現れやすくなる
「補足事項」
・この時期は、無意識に現実(外的由来)の情報による学習から「イメージ状態」が成長し、現実(外的
由来)の情報による影響から「エネルギー状態」が変化するため、周囲の家族は、現実(外的由来)の
情報を「プラス志向(自律)」にする「環境や体調」を整えることが大切になる
・この時期は、体の成長と共に脳(脳幹、大脳辺縁系)も成長し、立って歩くや言葉を話すことができ
るようになる
「幼稚園~小学校低学年(幼少期:4歳~9歳)」 ※図2.イメージ状態とエネルギー状態(幼少期)※
「イメージ状態」
・この時期は「脳内が対話の学習を始めた段階で周囲が気になり始める状態」だが、まだ「感性x自律」
の解釈による学習(記憶)が多く、心情の「イメージ状態:欲求のイメージ」が強い
※環境や体調に問題がある場合※
「環境や体調が気になる状態」のため、「感性x他律」の解釈による学習が増え、心情の「イメージ
状態:抑圧のイメージ」を強くする可能性がある
・「欲求のイメージ」が強いと、「好奇心、ワクワク」の直感が増える
・「抑圧のイメージ」が強いと、「猜疑心、ザワザワ」の直感が増える
「エネルギー状態」
・この時期は「脳内が対話の学習を始めた段階で周囲が気になり始める状態」だが、まだ「感性x自律」
の解釈による影響(是認)が多く、心情の「エネルギー状態:欲のエネルギー」が強い
※環境や体調に問題がある場合※
「環境や体調が気になる状態」のため、「感性x他律」の解釈による是認が増え、心情は「エネルギ
ー状態:疑のエネルギー」を強くする可能性がある
・「欲のエネルギー」が強いと、「喜び、笑い、愛好」の感情が増える
・「疑のエネルギー」が強いと、「苦しみ、叫び、嫌悪」の感情が増える
「心情の状態」
「欲求のイメージⅹ欲のエネルギー」の場合
・「欲求のイメージ」の行動トリガーは、「やりたい」の欲求から「好奇心」の直感が生まれ、「欲のエネ
ルギー」の行動ジャッジは、「自分が熱中する」状態で自分の直感を「許可する(諦めない)」判断にな
るため、「好奇心」を肯定した自律的な「行動」と「感情(喜び、笑い、愛好)」が現れやすくなる
「抑圧のイメージⅹ疑のエネルギー」の場合
・「抑圧のイメージ」の行動トリガーは、「やりたくない」の抑圧から「猜疑心」の直感が生まれ、「疑の
エネルギー」の行動ジャッジは、「周囲に過敏になる」状態で自分の直感を「許可しない(諦める)」の
判断になるため、「猜疑心」を正当化した他律的な「行動」と「感情(苦しみ、叫び、嫌悪)」が現れや
すくなる
「欲求のイメージⅹ疑のエネルギー」の場合
・「欲求のイメージ」の行動トリガーは、「やりたい」の欲求から「好奇心」の直感が生まれ、「疑のエネ
ルギー」の行動ジャッジは、「周囲に過敏になる」状態で自分の直感を「許可しない(諦める)」判断に
なるため、「好奇心」を正当化した他律的な「行動」と「感情(苦しみ、叫び、嫌悪)」が現れやすくなる
「抑圧のイメージⅹ欲のエネルギー」の場合
・「抑圧のイメージ」の行動トリガーは、「やりたくない」の抑圧から「猜疑心」の直感が生まれ、「欲の
エネルギー」の行動ジャッジは、「自分が熱中する」状態で自分の直感を「許可する(諦めない)」判断
になるため、「猜疑心」を肯定した自律的な「行動」と「感情(喜び、笑い、愛好)」が現れやすくなる
「補足事項」
・この時期は、各自が意識を持つことで、現実(外的由来)の情報と想像(内的由来)の情報による学習
から「イメージ状態」が成長し、現実(外的由来)の情報と想像(内的由来)の情報による影響から「エ
ネルギー状態」が変化するため、周囲の家族や教育者は、現実(外的由来)の情報や想像(内的由来)
の情報を「プラス志向(自律)」にする「環境や体調」を整えることが大切になる
・この時期は、大脳辺縁系に「個人志向(感性:曖昧なイメージ視点)」の解釈で学習するため、この時
期に「個性的な能力(芸術、スポーツ、言語など)」を鍛錬すると、その能力を「ネイティブな感覚」で
使えるようになる
「小学校高学年~中学校(成長期:10歳~15歳)」 ※図3.イメージ状態とエネルギー状態(成長・成年期)※
「イメージ状態」
・この時期は「脳内が社会の学習を始めた段階で周囲の視線が気になる状態」のため、「理性x自律」
や「理性x他律」の解釈による学習(記憶)が増え、心情の「イメージ状態:活力のイメージや制約の
イメージ」が強くなる
※環境や体調に問題がある場合※
「環境や体調が気になる状態」のため、「感性x他律」や「理性x他律」の解釈による学習が増え、
心情の「イメージ状態:抑圧のイメージ、制約のイメージ」を強くする可能性がある
・「欲求のイメージ」が強いと、「好奇心、ワクワク」の直感が増える
・「抑圧のイメージ」が強いと、「猜疑心、ザワザワ」の直感が増える
・「活力のイメージ」が強いと、「公共心、ニコニコ」の直感が増える
・「制約のイメージ」が強いと、「警戒心、ビクビク」の直感が増える
「エネルギー状態」
・この時期は「脳内が社会の学習を始めた段階で周囲の視線が気になる状態」のため、「理性x自律」
や「理性x他律」の解釈による影響(是認)が増え、心情の「エネルギー状態:愛のエネルギーや無の
エネルギー」が強くなる
※環境や体調に問題がある場合※
「環境や体調が気になる状態」のため、「感性x他律」や「理性x他律」の解釈による学習が増え、
心情の「エネルギー状態:疑のエネルギー、無のエネルギー」を強くする可能性がある
・「欲のエネルギー」が強いと、「喜び、笑い、愛好」の感情が増える
・「疑のエネルギー」が強いと、「苦しみ、叫び、嫌悪」の感情が増える
・「愛のエネルギー」が強いと、「楽しみ、驚き、安心」の感情が増える
・「無のエネルギー」が強いと、「恐れ、怒り、不安」の感情が増える
「心情の状態」
「欲求のイメージⅹ欲のエネルギー」の場合
・「欲求のイメージ」の行動トリガーは、「やりたい」の欲求から「好奇心」の直感が生まれ、「欲のエネ
ルギー」の行動ジャッジは、「自分が熱中する」状態で自分の直感を「許可する(諦めない)」判断にな
るため、「好奇心」を肯定した自律的な「行動」と「感情(喜び、笑い、愛好)」が現れやすくなる
「抑圧のイメージⅹ疑のエネルギー」の場合
・「抑圧のイメージ」の行動トリガーは、「やりたくない」の抑圧から「猜疑心」の直感が生まれ、「疑の
エネルギー」の行動ジャッジは、「周囲に過敏になる」状態で自分の直感を「許可しない(諦める)」の
判断になるため、「猜疑心」を正当化した他律的な「行動」と「感情(苦しみ、叫び、嫌悪)」が現れや
すくなる
「活力のイメージⅹ愛のエネルギー」の場合
・「活力のイメージ」の行動トリガーは、「やるべき」の欲求から「公共心」の直感が生まれ、「愛のエネ
ルギー」の行動ジャッジは、「自分が集中する」状態で自分の直感を「許可する(諦めない)」判断にな
るため、「公共心」を肯定した自律的な「行動」と「感情(楽しみ、驚き、安心)」が現れやすくなる
「制約のイメージⅹ無のエネルギー」の場合
・「制約のイメージ」の行動トリガーは、「やるべきでない」の抑圧から「警戒心」の直感が生まれ、「疑
のエネルギー」の行動ジャッジは、「周囲に敏感になる」状態で自分の直感を「許可しない(諦める)」
判断になるため、「警戒心」を正当化した他律的な「行動」と「感情(恐れ、怒り、不安)」が現れやす
くなる
「欲求のイメージⅹ疑のエネルギー」の場合
・「欲求のイメージ」の行動トリガーは、「やりたい」の欲求から「好奇心」の直感が生まれ、「疑のエネ
ルギー」の行動ジャッジは、「周囲に過敏になる」状態で自分の直感を「許可しない(諦める)」判断に
なるため、「好奇心」を正当化した他律的な「行動」と「感情(苦しみ、叫び、嫌悪)」が現れやすくなる
「抑圧のイメージⅹ欲のエネルギー」の場合
・「抑圧のイメージ」の行動トリガーは、「やりたくない」の抑圧から「猜疑心」の直感が生まれ、「欲の
エネルギー」の行動ジャッジは、「自分が熱中する」状態で自分の直感を「許可する(諦めない)」判断
になるため、「猜疑心」を肯定した自律的な「行動」と「感情(喜び、笑い、愛好)」が現れやすくなる
「活力のイメージⅹ無のエネルギー」の場合
・「活力のイメージ」の行動トリガーは、「やるべき」の欲求から「公共心」の直感が生まれ、「疑のエネ
ルギー」の行動ジャッジは、「周囲に敏感になる」状態で自分の直感を「許可しない(諦める)」判断に
なるため、「公共心」を正当化した他律的な「行動」と「感情(恐れ、怒り、不安)」が現れやすくなる
「制約のイメージⅹ愛のエネルギー」の場合
・「制約のイメージ」の行動トリガーは、「やるべきでない」の抑圧から「警戒心」の直感が生まれ、「愛
のエネルギー」の行動ジャッジは、「自分が集中する」状態で自分の直感を「許可する(諦めない)」の判
断になるため、「警戒心」を肯定した自律的な「行動」と「感情(喜び、笑い、愛好)」が現れやすくなる
「補足事項」
・この時期は、各自が意志を持ち行動し始めるので、現実(外的由来)の情報と想像(内的由来)の情報
による学習から「イメージ状態」が成長し、現実(外的由来)の情報と想像(内的由来)の情報による影
響から「エネルギー状態」が変化するため、周囲の家族や教育者は、現実(外的由来)の情報や想像
(内的由来)の情報を「プラス志向(自律)」にする「環境や体調」を整えることが大切になる
・この時期は、大脳新皮質に「社会志向(理性:明瞭なシステム視点)」の解釈で学習するため、この時
期に「合意的な目標達成、同意的な制約条件」を意識した「社会システムによる経験や体験」を学習す
ると、その能力を「ロジカルな感覚」で調和や調整を行えるようになる
・この時期は、自分の意志で行動し始めるため、「イメージ状態」に以下の個人差が現れやすい
(特に、実社会から学習する機会が増えるため、「イメージ状態」の社会志向が急成長しやすい)
1)プラス志向のエネルギー状態の場合
・社会志向(システム視点)で学習すると「活力のイメージ」が成長する
・個人志向(イメージ視点)で学習すると「欲求のイメージ」が成長する
2)マイナス志向のエネルギー状態の場合
・社会志向(システム視点)で学習すると「制約のイメージ」が成長する
・個人志向(イメージ視点)で学習すると「抑圧のイメージ」が成長する
・この時期の「抑圧のイメージx疑のエネルギー」状態の人には、特に細心の注意が必要になる
「抑圧のイメージ」だと、物事をイメージ視点(全体像)で解釈するため、社会のルールや仕組みに抑
圧を感じてしまい、「疑のエネルギー」だと、周囲に過敏になるため、疑心になりやすくサポートを
拒否する状態に陥りやすい
この状態になると、理性(社会志向)での解釈を強く嫌うため、大人の理詰めで説得すると状況を悪
化させやすいので、先に「プラス志向(自律)」にする「環境や体調」を整えることから始めた方が良い
「高校~大学(成年期:16歳~21歳)」 ※図3.イメージ状態とエネルギー状態(成長・成年期)※
「イメージ状態」
・この時期は「脳内が社会体験から学習する段階で周囲の反応が気になる状態」のため、「理性x自律」
や「理性x他律」の解釈による学習(記憶)が増え、心情の「イメージ状態:活力のイメージや制約の
イメージ」が強くなる
※環境や体調に問題がある場合※
「環境や体調が気になる状態」のため、「感性x他律」や「理性x他律」の解釈による学習が増え、
心情の「イメージ状態:抑圧のイメージ、制約のイメージ」を強くする可能性がある
・「欲求のイメージ」が強いと、「好奇心、ワクワク」の直感が増える
・「抑圧のイメージ」が強いと、「猜疑心、ザワザワ」の直感が増える
・「活力のイメージ」が強いと、「公共心、ニコニコ」の直感が増える
・「制約のイメージ」が強いと、「警戒心、ビクビク」の直感が増える
「エネルギー状態」
・この時期は「脳内が社会体験から学習する段階で周囲の反応が気になる状態」のため、「理性x自律」
や「理性x他律」の解釈による影響(是認)が増え、心情の「エネルギー状態:愛のエネルギーや無の
エネルギー」が強くなる
※環境や体調に問題がある場合※
「環境や体調が気になる状態」のため、「感性x他律」や「理性x他律」の解釈による学習が増え、
心情の「エネルギー状態:疑のエネルギー、無のエネルギー」を強くする可能性がある
・「欲のエネルギー」が強いと、「喜び、笑い、愛好」の感情が増える
・「疑のエネルギー」が強いと、「苦しみ、叫び、嫌悪」の感情が増える
・「愛のエネルギー」が強いと、「楽しみ、驚き、安心」の感情が増える
・「無のエネルギー」が強いと、「恐れ、怒り、不安」の感情が増える
「心情の状態」
「欲求のイメージⅹ欲のエネルギー」の場合
・「欲求のイメージ」の行動トリガーは、「やりたい」の欲求から「好奇心」の直感が生まれ、「欲のエネ
ルギー」の行動ジャッジは、「自分が熱中する」状態で自分の直感を「許可する(諦めない)」判断にな
るため、「好奇心」を肯定した自律的な「行動」と「感情(喜び、笑い、愛好)」が現れやすくなる
「抑圧のイメージⅹ疑のエネルギー」の場合
・「抑圧のイメージ」の行動トリガーは、「やりたくない」の抑圧から「猜疑心」の直感が生まれ、「疑の
エネルギー」の行動ジャッジは、「周囲に過敏になる」状態で自分の直感を「許可しない(諦める)」の
判断になるため、「猜疑心」を正当化した他律的な「行動」と「感情(苦しみ、叫び、嫌悪)」が現れや
すくなる
「活力のイメージⅹ愛のエネルギー」の場合
・「活力のイメージ」の行動トリガーは、「やるべき」の欲求から「公共心」の直感が生まれ、「愛のエネ
ルギー」の行動ジャッジは、「自分が集中する」状態で自分の直感を「許可する(諦めない)」判断にな
るため、「公共心」を肯定した自律的な「行動」と「感情(楽しみ、驚き、安心)」が現れやすくなる
「制約のイメージⅹ無のエネルギー」の場合
・「制約のイメージ」の行動トリガーは、「やるべきでない」の抑圧から「警戒心」の直感が生まれ、「疑
のエネルギー」の行動ジャッジは、「周囲に敏感になる」状態で自分の直感を「許可しない(諦める)」
判断になるため、「警戒心」を正当化した他律的な「行動」と「感情(恐れ、怒り、不安)」が現れやす
くなる
「欲求のイメージⅹ疑のエネルギー」の場合
・「欲求のイメージ」の行動トリガーは、「やりたい」の欲求から「好奇心」の直感が生まれ、「疑のエネ
ルギー」の行動ジャッジは、「周囲に過敏になる」状態で自分の直感を「許可しない(諦める)」判断に
なるため、「好奇心」を正当化した他律的な「行動」と「感情(苦しみ、叫び、嫌悪)」が現れやすくなる
「抑圧のイメージⅹ欲のエネルギー」の場合
・「抑圧のイメージ」の行動トリガーは、「やりたくない」の抑圧から「猜疑心」の直感が生まれ、「欲の
エネルギー」の行動ジャッジは、「自分が熱中する」状態で自分の直感を「許可する(諦めない)」判断
になるため、「猜疑心」を肯定した自律的な「行動」と「感情(喜び、笑い、愛好)」が現れやすくなる
「活力のイメージⅹ無のエネルギー」の場合
・「活力のイメージ」の行動トリガーは、「やるべき」の欲求から「公共心」の直感が生まれ、「疑のエネ
ルギー」の行動ジャッジは、「周囲に敏感になる」状態で自分の直感を「許可しない(諦める)」判断に
なるため、「公共心」を正当化した他律的な「行動」と「感情(恐れ、怒り、不安)」が現れやすくなる
「制約のイメージⅹ愛のエネルギー」の場合
・「制約のイメージ」の行動トリガーは、「やるべきでない」の抑圧から「警戒心」の直感が生まれ、「愛
のエネルギー」の行動ジャッジは、「自分が集中する」状態で自分の直感を「許可する(諦めない)」の判
断になるため、「警戒心」を肯定した自律的な「行動」と「感情(喜び、笑い、愛好)」が現れやすくなる
「補足事項」
・この時期は、各自が意志を持ち社会で行動し始めるので、現実(外的由来)の情報と想像(内的由来)
の情報による学習から「イメージ状態」が成長し、現実(外的由来)の情報と想像(内的由来)の情報に
よる影響から「エネルギー状態」が変化するため、周囲の家族や関係者は、「プラス志向(自律)」の成
長を促すために必要な「アドバイス、サポート」行うことが大切になる
・この時期も、大脳新皮質に「社会志向(理性:明瞭なシステム視点)」の解釈で学習するため、この時
期に「合意的な目標達成、同意的な制約条件」を意識した「社会システムによる経験や体験」を学習す
ると、その能力を「ロジカルな感覚」で調和や調整を行えるようになる
・この時期は、自分の意志で大きく行動するため、「イメージ状態」に以下の変化も大きく現れやすい
(特に、高校や大学の入学や引越しなどの環境変化から、「エネルギー状態」も大きく変化しやすい)
1)プラス志向のエネルギー状態の場合
・社会志向(システム視点)で学習すると「活力のイメージ」が成長する
・個人志向(イメージ視点)で学習すると「欲求のイメージ」が成長する
2)マイナス志向のエネルギー状態の場合
・社会志向(システム視点)で学習すると「制約のイメージ」が成長する
・個人志向(イメージ視点)で学習すると「抑圧のイメージ」が成長する
・この時期の「抑圧のイメージx疑のエネルギー」状態の人には、細心の注意が必要になる
「抑圧のイメージ」だと、物事をイメージ視点(全体像)で解釈するため、社会のルールや仕組みに抑
圧を感じてしまい、「疑のエネルギー」だと、周囲に過敏になるため、疑心になりやすくサポートを
拒否する状態に陥りやすい
この状態になると、理性(社会志向)での解釈を強く嫌うため、大人の理詰めで説得すると状況を悪
化させやすいので、先に「プラス志向(自律)」にする「環境や体調」を整えることから始めた方が良い
「社会人1~6年目(成年期:22歳~27歳)」 ※図3.イメージ状態とエネルギー状態(成長・成年期)※
「イメージ状態」
・この時期は「脳内が社会活動から学習する段階で周囲の反応が気になる状態」のため、「理性x自律」
や「理性x他律」の解釈による学習(記憶)が増え、心情の「イメージ状態:活力のイメージや制約の
イメージ」が強くなる
※環境や体調に問題がある場合※
「環境や体調が気になる状態」のため、「感性x他律」や「理性x他律」の解釈による学習が増え、
心情の「イメージ状態:抑圧のイメージ、制約のイメージ」を強くする可能性がある
・「欲求のイメージ」が強いと、「好奇心、ワクワク」の直感が増える
・「抑圧のイメージ」が強いと、「猜疑心、ザワザワ」の直感が増える
・「活力のイメージ」が強いと、「公共心、ニコニコ」の直感が増える
・「制約のイメージ」が強いと、「警戒心、ビクビク」の直感が増える
「エネルギー状態」
・この時期は「脳内が社会活動から学習する段階で周囲の反応が気になる状態」のため、「理性x自律」
や「理性x他律」の解釈による影響(是認)が増え、心情の「エネルギー状態:愛のエネルギーや無の
エネルギー」が強くなる
※環境や体調に問題がある場合※
「環境や体調が気になる状態」のため、「感性x他律」や「理性x他律」の解釈による学習が増え、
心情の「エネルギー状態:疑のエネルギー、無のエネルギー」を強くする可能性がある
・「欲のエネルギー」が強いと、「喜び、笑い、愛好」の感情が増える
・「疑のエネルギー」が強いと、「苦しみ、叫び、嫌悪」の感情が増える
・「愛のエネルギー」が強いと、「楽しみ、驚き、安心」の感情が増える
・「無のエネルギー」が強いと、「恐れ、怒り、不安」の感情が増える
「心情の状態」
「欲求のイメージⅹ欲のエネルギー」の場合
・「欲求のイメージ」の行動トリガーは、「やりたい」の欲求から「好奇心」の直感が生まれ、「欲のエネ
ルギー」の行動ジャッジは、「自分が熱中する」状態で自分の直感を「許可する(諦めない)」判断にな
るため、「好奇心」を肯定した自律的な「行動」と「感情(喜び、笑い、愛好)」が現れやすくなる
「抑圧のイメージⅹ疑のエネルギー」の場合
・「抑圧のイメージ」の行動トリガーは、「やりたくない」の抑圧から「猜疑心」の直感が生まれ、「疑の
エネルギー」の行動ジャッジは、「周囲に過敏になる」状態で自分の直感を「許可しない(諦める)」の
判断になるため、「猜疑心」を正当化した他律的な「行動」と「感情(苦しみ、叫び、嫌悪)」が現れや
すくなる
「活力のイメージⅹ愛のエネルギー」の場合
・「活力のイメージ」の行動トリガーは、「やるべき」の欲求から「公共心」の直感が生まれ、「愛のエネ
ルギー」の行動ジャッジは、「自分が集中する」状態で自分の直感を「許可する(諦めない)」判断にな
るため、「公共心」を肯定した自律的な「行動」と「感情(楽しみ、驚き、安心)」が現れやすくなる
「制約のイメージⅹ無のエネルギー」の場合
・「制約のイメージ」の行動トリガーは、「やるべきでない」の抑圧から「警戒心」の直感が生まれ、「疑
のエネルギー」の行動ジャッジは、「周囲に敏感になる」状態で自分の直感を「許可しない(諦める)」
判断になるため、「警戒心」を正当化した他律的な「行動」と「感情(恐れ、怒り、不安)」が現れやす
くなる
「欲求のイメージⅹ疑のエネルギー」の場合
・「欲求のイメージ」の行動トリガーは、「やりたい」の欲求から「好奇心」の直感が生まれ、「疑のエネ
ルギー」の行動ジャッジは、「周囲に過敏になる」状態で自分の直感を「許可しない(諦める)」判断に
なるため、「好奇心」を正当化した他律的な「行動」と「感情(苦しみ、叫び、嫌悪)」が現れやすくなる
「抑圧のイメージⅹ欲のエネルギー」の場合
・「抑圧のイメージ」の行動トリガーは、「やりたくない」の抑圧から「猜疑心」の直感が生まれ、「欲の
エネルギー」の行動ジャッジは、「自分が熱中する」状態で自分の直感を「許可する(諦めない)」判断
になるため、「猜疑心」を肯定した自律的な「行動」と「感情(喜び、笑い、愛好)」が現れやすくなる
「活力のイメージⅹ無のエネルギー」の場合
・「活力のイメージ」の行動トリガーは、「やるべき」の欲求から「公共心」の直感が生まれ、「疑のエネ
ルギー」の行動ジャッジは、「周囲に敏感になる」状態で自分の直感を「許可しない(諦める)」判断に
なるため、「公共心」を正当化した他律的な「行動」と「感情(恐れ、怒り、不安)」が現れやすくなる
「制約のイメージⅹ愛のエネルギー」の場合
・「制約のイメージ」の行動トリガーは、「やるべきでない」の抑圧から「警戒心」の直感が生まれ、「愛
のエネルギー」の行動ジャッジは、「自分が集中する」状態で自分の直感を「許可する(諦めない)」の判
断になるため、「警戒心」を肯定した自律的な「行動」と「感情(喜び、笑い、愛好)」が現れやすくなる
「補足事項」
・この時期は、各自が意志を持ち社会で活動し始めるので、現実(外的由来)の情報と想像(内的由来)
の情報による学習から「イメージ状態」が成長し、現実(外的由来)の情報と想像(内的由来)の情報に
よる影響から「エネルギー状態」が変化するため、周囲の家族や関係者は、「プラス志向(自律)」の成
長を促すために必要な「アドバイス、サポート」行うことが大切になる
・この時期も、大脳新皮質に「社会志向(理性:明瞭なシステム視点)」の解釈で学習するため、この時
期に「合意的な目標達成、同意的な制約条件」を意識した「社会システムによる経験や体験」を学習す
ると、その能力を「ロジカルな感覚」で調和や調整を行えるようになる
・この時期は、自分の責任で大きく行動するため、「イメージ状態」に以下の変化も大きく現れやすい
(特に、会社の入社や引越しなどの環境変化から、「エネルギー状態」も大きく変化しやすい)
1)プラス志向のエネルギー状態の場合
・社会志向(システム視点)で学習すると「活力のイメージ」が成長する
・個人志向(イメージ視点)で学習すると「欲求のイメージ」が成長する
2)マイナス志向のエネルギー状態の場合
・社会志向(システム視点)で学習すると「制約のイメージ」が成長する
・個人志向(イメージ視点)で学習すると「抑圧のイメージ」が成長する
・この時期の「抑圧のイメージx疑のエネルギー」状態の人には、細心の注意が必要になる
「抑圧のイメージ」だと、物事をイメージ視点(全体像)で解釈するため、社会のルールや仕組みに抑
圧を感じてしまい、「疑のエネルギー」だと、周囲に過敏になるため、疑心になりやすくサポートを
拒否する状態に陥りやすい
この状態になると、理性(社会志向)での解釈を強く嫌うため、大人の理詰めで説得すると状況を悪
化させやすいので、先に「プラス志向(自律)」にする「環境や体調」を整えることから始めた方が良い
「成長タイプ」は、以下の通りになる
一般的な成長タイプは、社会志向の「意識、思考、環境、体調」により、「支援、支配」の印象が強くなる
・「支援」タイプ:合意的な目標達成を優先する「調和型」
・「支配」タイプ:同意的な制約条件を優先する「調整型」
個性優先の成長タイプは、個人志向の「意識、思考、環境、体調」により、「支離」の印象が強くなる
・「支離」タイプ:恣意的な達成意欲を優先する「独創型」
特殊環境の成長タイプは、個人志向の「意識、思考、環境、体調」により、「支障」の印象が強くなる
・「支障」タイプ:失意的な現実逃避を優先する「疑念型」
以上の「心情の成長過程」や「成長タイプ」を理解することで、次の「育成方針」が可能になる
「育成方針(案)」は、以下の通りになる
一般的な成長タイプの場合
「小学校:社会志向の基礎、個人志向の探求」
社会志向の基礎(支援、支配)、個人志向の探求(支離)を「学習目標」にする
・「支援」とは、合意的な目標達成を意識させる「調和型の達成行動」の基礎を学ぶ
・「支配」とは、同意的な制約条件を意識させる「調整型の規則行動」の基礎を学ぶ
・「支離」とは、衝動的な達成意欲を意識させる「独創型の意欲行動」を探求する
「中学校:社会志向の経験、個人志向の探求」
社会志向の経験(支援、支配)、個人志向の探求(支離)を「育成目標」にする
「支援」とは、合意的な目標達成を意識させる「調和型の達成行動」を経験する
「支配」とは、同意的な制約条件を意識させる「調整型の規則行動」を経験する
「支離」とは、衝動的な達成意欲を意識させる「独創型の意欲行動」を探求する
「高校~大学:社会志向の活用、個人志向の活用」
社会志向の活用(支援、支配)、個人志向の活用(支離)を「活動目標」にする
「支援」とは、合意的な目標達成を意識した「調和型の達成行動」を活用する
「支配」とは、同意的な制約条件を意識した「調整型の規則行動」を活用する
「支離」とは、衝動的な達成意欲を意識した「独創型の意欲行動」を活用する
個性優先な成長タイプの場合
個性優先の場合、「育成方針」の配慮が必要になる
例えば、個性の強い人は、「欲求」の分布領域が強く、恣意的な達成意欲を優先する「独創型」が多い
その「独創型」であることが、「個性の育成」に不可欠であり、安易に「社会志向の制約」を強めると、
原動力である「欲求のイメージ、欲のエネルギー(+)」を失う可能性がある
「個性優先」の育成方針には、次の「2パターン」がある
①「欲求のイメージ」を強化し、他者が「社会的対応」を仲介サポートする
(「制約のイメージ」を排除し、集中的に「欲求のイメージ」を伸ばす。そして、他者が「制約のイメ
ージ、活力のイメージ」による対応を仲介サポートする)
②「欲求のイメージ、活力のイメージ」を、同時に強化する
(「活力のイメージ」を指導し、自身の目標設定で「欲求のイメージ」も伸ばす)
理想は、②の「調和型の成長」であるが、①の「恣意型の制御」も間違いとは言えない
特殊環境の成長タイプの場合
特殊環境の場合、「育成方針」の配慮が必要になる
例えば、特殊環境の人は、「抑圧」の分布領域が強く、失意的な現実逃避を優先する「疑念型」が多い
その「疑念型」であることが「救済の拒絶」を起こす原因であり、安易に「プラス志向」の発言を行うと、
心情が「抑圧のイメージ」の「思考の繰返し」を行い、「マイナス志向」のイメージ状態を強める可能性
がある
「特殊環境(従属状態、体調不良など)」の育成方針には、次の「2パターン」がある
①特殊環境を改善できる場合、環境の改善後、心情を回復サポートする
(環境による「疑のエネルギー」を排除し、「抑圧のイメージ」の思考の繰返しを止め、自身の目標
設定で「活力のイメージ、欲求のイメージ」の「思考の繰返し」を増やす)
②特殊環境を改善できない場合、意識的に心情を回復サポートする
(「心情の環境づくり」を提案し、意識して「抑圧のイメージ」の思考の繰返しを止め、自身の目標
設定で「活力のイメージ、欲求のイメージ」の「思考の繰返し」を増やす)
理想は、①の「環境改善」であるが、②の「意識改革」でも効果はある
ただ、「救済の拒絶」を起こす状態なら、すぐ病院に相談した方が良い
現在は、根幹の原因を治療する手段もある
「意識的に心情を回復サポートする」とは、
次の「無自覚な思考を確認する方法」と「回復サポートの手順」のことである
この方法と手順で、心情を意識し回復サポートを行う
「無自覚な思考を確認する方法」
①休憩、就寝前などの「心が落ち着いた」時、「どんな思考状態か」を確認する
その時、「抑圧のイメージ(不満、執念、執着)」や支障(従属、偏見、疑念、疑念型、過去志向、
抑圧、疑)の印象なら、「イメージ状態」の「抑圧のイメージ(過去の悪いイメージ)」が強いので、
原因となる思考停止を行う必要がある
②次の事象を感じるか確認する
「異様にお腹が減る」「食べても体重が増えない」
「些細なことに感情が大きく反応する」「なんかピリピリを感じる」
この事象があるなら、「エネルギー状態」の「疑のエネルギー、無のエネルギー」が強い可能性が
あるため、原因となる環境改善か思考停止を行う必要がある
「回復サポートの手順」
①常に「抑圧のイメージ(不満、執念、執着)の思考」をしていないか確認し、思考を繰返さない
②常に「周囲に過敏な反応」をしていないか確認し、過敏な反応を繰返さない
③「欲求のイメージ(衝動、意欲、貪欲)、活力のイメージ(英気、勇気、根気)」となる目標設定を
行い、その計画や実施のため思考を繰返す
この幼少期~成年期の「成長過程」は、現在でも同様の教育が実施されている
ただ、一部の個人解釈により、捻じ曲がる実態もあるため、体系化の明瞭化が必要と感じている
そして、個性優先・特殊環境の「育成方針」は、今後の教育ため大事であると感じている
<心情の意識改善(印象確認、目標設定)>
「印象」の体系化より、「支離、支援、支配、支障」の姿を確認する
そして、自分の望む「意識、心情、行動」の姿を選択し、「目標設定」を意識する
「イメージ状態」は、日常の「外的情報(環境、体調)と内的情報(意識、思考)」から思考し、「情報と感覚
(直感)」を「記憶(感覚のイメージ化)」することで、その蓄積により「イメージ状態」を変化させていく
そして、この流れは「無自覚な思考」で行われる
この「イメージ状態」を制御する方法は、日常の内的情報(意識)から変化を加え、自然に「イメージ状態」
を自分の望む方向に変化させていくしかない
「日常からイメージ状態を変化させる目標設定の方法」
※「プラス志向のイメージ」の記憶に導く目標設定を意識する
「印象」の体系化には、内的情報(意識)となる「意識、心情、行動」の姿をまとめている
この体系化から、自分の望む「意識、心情、行動」の姿を確認し、その姿を「目標設定」とすることで、
「イメージ状態」を自分の望む方向に導いていける
また、「イメージ状態」の変化は、「無自覚な思考」にも良い効果を与えると考えている
ただ、この方法はイメージ学習に時間を要するため、計画的に幼少期から教育環境を管理していくこ
とが望ましいが、日常生活における「無自覚な言動」が「自覚した言動」に変わる効果も期待できるため、
大人だからもう遅いと考えないで対応してほしい
「目標設定」は、自分の望む「意識、心情、行動」の姿を確認し、「イメージ状態」を自分の望む方向へ導く
ことで、「無自覚な言動」にも良い効果を与えられる
また、日常生活の「無自覚な言動」が「自覚した言動」に変わる効果もあるあるので、ネット社会における
「無自覚な言動」の問題対策としても、日常生活での「意識改善」は大切だと考えている
<心情の思考改善(思考維持、思考回避)>
「心情」の体系化より、「過程1(イメージ状態)」を確認する
そして、「外的思考、内的思考」の仕組みを理解し、「思考維持と思考回避」を意識する
「思考維持」とは、自分を「プラス志向」にする「外的思考、内的思考」を増やす
「思考回避」とは、自分を「マイナス志向」にする「内的思考の繰返し」を止めるか減らす
「思考維持」が必要な理由は、プラス志向の「イメージ状態」を維持するには、日常のプラス志向の
出来事に関する思考を増やすことで、「外的思考(知識、経験)、内的思考(想像)」による記憶(感覚
のイメージ化)を増やし、プラス志向のイメージを蓄積していくことが大切になる
そして、その維持を適切に行うためには、各自の判断で実施するため、事前に「思考維持」を理解
し、日常に取入れていく必要があると考えている
この「思考維持」では、日常のプラス志向の出来事に関する思考を増やすため、どのような思考が
必要なのか、事例で「プラス志向とマイナス志向の違い」を提示し説明する
「日常からプラス志向の記憶を増やす方法」
※「プラス志向のイメージ」の記憶を増やす日常生活を意識する
例1.「ある商品を値引きしてほしい」と言われたが、「新商品で値引きできない」状況だった場合
①「その商品は新商品のため値引きできません」
この回答だと、相手には「マイナス志向のイメージ」しか残らないで終わるし、相手が不機嫌にな
ると、自分も「マイナス志向のイメージ」を受取ることになる
②「その商品は新商品のため値引きできませんが、他の商品ならお値引きできるものもあります」
この回答だと、「目的と金額の見合う商品」が提案できれば、互いに「プラス志向のイメージ」で
解決できるし、商談成立しなくても、相手には「プラス志向のイメージ」が残ることになる
この違いは、「イメージ状態」の違いから来ている
①「制約のイメージ(やらされること)」が強い状態で、無自覚な「警戒心」から適当な回答を考える
②「活力のイメージ(やるべきこと)」が強い状態で、無自覚な「公共心」から最適な回答を考える
これは、作業者なら「①で正解」で、経営者なら「②が正解」なのかもしれない
ただ、将来的に経営者を目指すなら、「WinWinの解決」の②を体験したほうが良い
そして、顧客対応の「成功体験」を増やすことが、「日常からプラス志向の記憶を増やす方法」であり、
結果的にプラス志向の「イメージ状態」が維持できる
「思考維持」は、誰でも必ずやる必要性はないが、日々精進した人との差は将来的に大きく現れるの
で、日常生活での「思考改善」は大切だと考えている
「思考回避」が必要な理由は、マイナス志向の「イメージ状態」を回避するには、日常のマイナス志
向の出来事に関する思考を減らすことで、「外的思考(知識、経験)、内的思考(想像)」による記憶
(感覚のイメージ化)を減らし、マイナス志向のイメージを蓄積させないことが大切になる
そして、その回避を適切に行うためには、各自の判断で実施するため、事前に「思考回避」を理解
し、日常に取入れていく必要があると考えている
この「思考回避」では、日常のマイナス志向の出来事に関する思考を減らすため、どのような思考
が不要なのか、事例で「マイナス志向に陥る出来事」を提示し説明する
「日常からマイナス志向の記憶を止めるか減らす方法」
※「マイナス志向のイメージ」の記憶を繰返さない日常生活を意識する
例2.相手に「お金を節約しなさい」と指導し、その問題解決できない状況が続いた場合
相手に「お金を節約しなさい」と指導した時点で、物事を「警戒心」で記憶(感覚のイメージ化)してい
るので、自然に「制約のイメージ」が強くなり始める
そして、問題解決できない状況が続くと、節約させる方法を「内的思考(想像)」で考え始める
さらに、問題解決できない状況が続くと、節約させる方法を「内的思考(想像)の繰返し」で考え始める
この「内的思考(想像)の繰返し」は、その思考を「減らすか停止する」段階と考えるべき
なぜなら、もう節約させる方法に「執念、執着」がある状況だから
このプロセスの恐ろしい所は、社会志向(システム的視点の解釈)による「順守や責任」の指導が、問
題解消できないことで、個人志向(イメージ的視点の解釈)による「執念、執着」に変化していくこと
もしこの段階で「内的思考(想像)の繰返し」を止めないと、その相手に対する「抑圧のイメージ」が強
く残ることになる。例えば、顔を見ただけで「怒りの感情」が抑えられなくなるとか
「内的思考(想像)の繰返し」を感じたら、その思考に時間を与えないことが大事になる
例えば、他の「プラス志向のイメージ」を思考を増やすことが、「日常からマイナス志向の記憶を止め
るか減らす方法」であり、自分の身を守る方法だと考えている
「思考回避」は、日常生活に継続性のある問題がなければ、あまり気にする必要はないが、誰でも陥り
やすい状況から発展していくので、日常生活での「思考改善」は大切だと考えている
<心情の環境改善(環境対策、体調管理)>
「心情」の体系化より、「過程2(エネルギー状態)」を確認する
そして、「エネルギー状態」の仕組みを理解し、「環境対策と体調管理」を意識する
「環境対策」とは、「マイナス志向のエネルギー」となる「環境要因(個人、組織、場所など)」を対策する
「体調管理」とは、「マイナス志向のエネルギー」となる「体調不良」を管理する
「環境対策」が必要な理由は、マイナス志向の「エネルギー状態」を対策するには、日常のマイナス
志向の出来事を「回避、改善、移動」することで、「外的思考(知識、経験)、内的思考(想像)」によ
る是認(感覚のエネルギー化)を減らし、マイナス志向のエネルギーを蓄積させないことが大切に
なる
そして、その対策を適切に行うためには、各自の判断で実施するため、事前に「環境対策」を理解
し、日常に取入れていく必要があると考えている
この「環境対策」では、日常のマイナス志向の出来事を「回避、改善、移動」するため、どのような
環境要因が不要なのか、事例で「マイナス志向に導く出来事」を提示し説明する
「環境要因(個人、組織、場所など)を対策する方法」
※「プラス志向のエネルギー」を是認できる環境対策を意識する
例1.既存環境の改善提案を「普通出来ないでしょ、挑戦するのは無鉄砲」と真剣に聞かない場合
既存環境の変化を嫌う「個人や組織」は、物事を「現在思考(過去~現在)」で判断する傾向がある
そして、物事を「未来思考(現在~未来)」で考えた改善提案を真剣に理解せず、自分を「正当化」す
るため、「失敗したら責任取れるの?、失敗したとき後悔するよ」などの「相手を抑圧する言動」に
より、「相手の意思で諦める」ように誘導する
この「あなたが心配だから」という言動に「論点をずらされた」と感じたなら、その「個人」は「相談に
相応しい人ではない」と考えた方が良い(ただし、真剣に聞いて「あなたが心配だから」は別である)
もし「組織、場所」に、このような物事を「現在思考(過去~現在)」で判断する人が多いと感じている
なら、その既存環境に「大きな変化を与える」ことは難しいと考えた方が良い
以上を参考に…
「マイナス志向のエネルギー」を感じる「個人、組織、場所」に、我慢できる「メリット」が多いなら、
無理をして「環境対策」を行う必要はない
「マイナス志向のエネルギー」を感じる「個人、組織、場所」に、我慢できない「デメリット」が多いな
ら、計画的に「環境対策」を行う必要がある
この「環境対策」は、大きく3つに分かれると考えている
①「マイナス志向のエネルギー」を感じる「個人、組織、場所」を回避する
(周囲に敏感や過敏にならない環境で回避する)
②「マイナス志向のエネルギー」を感じる「個人、組織、場所」を改善する
(同じ意志と持つ人達と計画的な推進で改善する)
③「プラス志向のエネルギー」を感じる「個人、組織、場所」へ移動する
(自分に熱中や集中する環境へ移動する)
「環境対策」は、日常生活が「自分に熱中や集中する」状態なら、環境に変化を与える必要はないが、
日常生活が「周囲に敏感や過敏にする」状態なら、環境に変化を与える決断をすべきだ考えている
環境を放置することは、人生の大切な時間を無駄づかいする行為なので
「体調管理」が必要な理由は、マイナス志向の「エネルギー状態」を管理するには、日常のマイナス
志向の体調不良を「回避、改善」することで、「外的思考(知識、経験)、内的思考(想像)」による是
認(感覚のエネルギー化)を減らし、マイナス志向のエネルギーを蓄積させないことが大切になる
そして、その管理を適切に行うためには、各自の判断で実施するため、事前に「体調管理」を理解
し、日常に取入れていく必要があると考えている
この「体調管理」では、日常のマイナス志向の体調不良を「回避、改善」するため、どのような体調
管理が必要なのか、事例で「マイナス志向に導く体調不良」を提示し説明する
「体調不良を管理する方法」
※「マイナス志向のエネルギー」を是認させない体調管理を意識する
例3.体調不良の期間が長く「何か自信がない、何か不安になる」と感じている場合
体調不良(胃腸など)の期間が長く続き、「周囲に敏感や過敏になる」状態なら、体調不良の影響で
「エネルギー状態」が「マイナス志向のエネルギー」を蓄積している
そして、「イメージ状態」も「マイナス思考のイメージ」が蓄積し、「警戒心や猜疑心」も強くなる
この状態になると「何か自信がない、何か不安になる」などの症状が現れる
体調不良(胃腸など)の危険な所は、体調の感覚が社会志向(システム的視点の解釈)で理解できず、
個人志向(イメージ的視点の解釈)の理解となり、「イメージ状態」が「制約のイメージ(約束、順守、
責任)」ではなく「抑圧イメージ(不満、執念、執着)」が蓄積していくことである
以上を考慮し…
この「体調管理」は、大きく2つに分かれると考えている
①「マイナス志向のエネルギー」を感じる「体調不良」による「マイナス志向のイメージ」を回避する
(プラス志向の出来事を増やす「思考維持」で、マイナス志向のイメージ状態を回避する)
②「マイナス志向のエネルギー」を感じる「体調不良」を改善する
(根本原因の体調不良を改善する)
「体調管理」は、体調が良ければ、あまり気にする必要はないが、今は元気な人でも体調不良にな
る可能性があるので、事前に「体調不良の危険な所」を理解することは大切だと考えている
2)「心得」の図解
<心情の分布領域(成長過程)>
「図4.イメージ状態とエネルギー状態」には、幼少期(幼稚園の入園前、幼稚園~小学校低学年)、
成長期・青年期(小学校高学年~社会人)の分布領域を表現している
図4.イメージ状態とエネルギー状態(◆:分布・強、◇:分布・中、△分布・弱)
<幼少期(幼稚園の入園前)・支離:独創型>
イメージ状態 :欲求(強)、抑圧(弱)
エネルギー状態:欲(強)、疑(弱)
プラス プラス
| ◆◆◆◆ | ◆◆◆◆
| ◆◆◆◆ | ◆◆◆◆
| ◆◆◆◆ | ◆◆◆◆
社会ーーーーーー+ーーーーーー個人 社会ーーーーーー+ーーーーーー個人
| △△△△ | △△△△
| △△△△ | △△△△
| △△△△ | △△△△
マイナス マイナス
「イメージ状態:欲求」 「エネルギー状態:欲」
<幼少期(幼稚園~小学校低学年)・支離:独創型>
イメージ状態 :欲求(強)、抑圧(弱)、活力(弱)、制約(弱)
エネルギー状態:欲(強)、疑(弱)、愛(弱)、無(弱)
プラス プラス
△△△△ | ◆◆◆◆ △△△△ | ◆◆◆◆
△△△△ | ◆◆◆◆ △△△△ | ◆◆◆◆
△△△△ | ◆◆◆◆ △△△△ | ◆◆◆◆
社会ーーーーーー+ーーーーーー個人 社会ーーーーーー+ーーーーーー個人
△△△△ | △△△△ △△△△ | △△△△
△△△△ | △△△△ △△△△ | △△△△
△△△△ | △△△△ △△△△ | △△△△
マイナス マイナス
「イメージ状態:欲求」 「エネルギー状態:欲」
<成長期・成年期(小学校高学年~社会人)・支離:独創型>
イメージ状態 :欲求(強)、抑圧(中)、活力(弱)、制約(弱)
エネルギー状態:欲(強)、疑(中)、愛(弱)、無(弱)
プラス プラス
△△△△ | ◆◆◆◆ △△△△ | ◆◆◆◆
△△△△ | ◆◆◆◆ △△△△ | ◆◆◆◆
△△△△ | ◆◆◆◆ △△△△ | ◆◆◆◆
社会ーーーーーー+ーーーーーー個人 社会ーーーーーー+ーーーーーー個人
△△△△ | ◇◇◇◇ △△△△ | ◇◇◇◇
△△△△ | ◇◇◇◇ △△△△ | ◇◇◇◇
△△△△ | ◇◇◇◇ △△△△ | ◇◇◇◇
マイナス マイナス
「イメージ状態:欲求」 「エネルギー状態:欲」
<成長期・成年期(小学校高学年~社会人)・支障:疑念型>
イメージ状態は、抑圧(強)、欲求(中)、活力(弱)、制約(弱)
エネルギー状態は、疑(強)、欲(中)、愛(弱)、無(弱)
プラス プラス
△△△△ | ◇◇◇◇ △△△△ | ◇◇◇◇
△△△△ | ◇◇◇◇ △△△△ | ◇◇◇◇
△△△△ | ◇◇◇◇ △△△△ | ◇◇◇◇
社会ーーーーーー+ーーーーーー個人 社会ーーーーーー+ーーーーーー個人
△△△△ | ◆◆◆◆ △△△△ | ◆◆◆◆
△△△△ | ◆◆◆◆ △△△△ | ◆◆◆◆
△△△△ | ◆◆◆◆ △△△△ | ◆◆◆◆
マイナス マイナス
「イメージ状態:抑圧」 「エネルギー状態:欲」
<成長期・成年期(小学校高学年~社会人)・支援:調和型>
イメージ状態は、活力(強)、制約(弱)、欲求(中)、抑圧(弱)
エネルギー状態は、愛(強)、無(弱)、欲(中)、疑(弱)
プラス プラス
◆◆◆◆ | △△△△ ◆◆◆◆ | △△△△
◆◆◆◆ | △△△△ ◆◆◆◆ | △△△△
◆◆◆◆ | △△△△ ◆◆◆◆ | △△△△
社会ーーーーーー+ーーーーーー個人 社会ーーーーーー+ーーーーーー個人
◇◇◇◇ | △△△△ ◇◇◇◇ | △△△△
◇◇◇◇ | △△△△ ◇◇◇◇ | △△△△
◇◇◇◇ | △△△△ ◇◇◇◇ | △△△△
マイナス マイナス
「イメージ状態:活力」 「エネルギー状態:愛」
<成長期・成年期(小学校高学年~社会人)・支配:調整型>
イメージ状態は、制約(強)、活力(中)、欲求(弱)、抑圧(弱)
エネルギー状態は、無(強)、愛(中)、欲(弱)、疑(弱)
プラス プラス
◇◇◇◇ | △△△△ ◇◇◇◇ | △△△△
◇◇◇◇ | △△△△ ◇◇◇◇ | △△△△
◇◇◇◇ | △△△△ ◇◇◇◇ | △△△△
社会ーーーーーー+ーーーーーー個人 社会ーーーーーー+ーーーーーー個人
◆◆◆◆ | △△△△ ◆◆◆◆ | △△△△
◆◆◆◆ | △△△△ ◆◆◆◆ | △△△△
◆◆◆◆ | △△△△ ◆◆◆◆ | △△△△
マイナス マイナス
「イメージ状態:制約」 「エネルギー状態:欲」